漢方の知恵袋
下痢漢方養生で「下痢」体質を改善!
監修:菅沼 栄先生(中医学講師)
適切な対処で「下痢」体質の改善を
check!下痢体質を改善!タイプ別「下痢」の対処法
【急性下痢】前触れなく、突然起こる下痢。ほとんどの症状は自然に改善されますが、胃腸の不調を放置すると慢性下痢につながることも。油断をせず、胃腸の働きが整うまでしっかりケアしましょう。【慢性下痢】繰り返し起こる下痢。症状が1カ月以上続く場合は慢性化していると考えましょう。日頃の養生を心がけ、弱っている胃腸の働きを整えることが大切です。
1 急性下痢①冷たい飲食物に注意「冷え」タイプ

- 気になる症状
突然の腹痛・下痢(薄く臭いが少ない)、お腹がゴロゴロ鳴る、食欲不振、胃のムカつき、膨満感、悪寒、頭痛、発熱、舌苔が白く薄い
- 改善ポイント
- 胃腸は冷えに弱い臓器。冷たいものを取り過ぎたり、寒さで身体が冷えたりすると、下痢を起こす要因となります。このタイプは、身体をしっかり温めて冷えを取り除くことが大切です。
- 摂り入れたい食材
冷えを取り除き胃腸の働きを整える:しょうが、ねぎ、しそ、にんにく、らっきょう など
2 急性下痢②食中毒など「熱」タイプ

- 気になる症状
突然の腹痛、下痢(粘液便、臭いが強い)、残便感、肛門の熱感、吐き気、胃痛、口渇、発熱、尿が黄色い、舌苔が黄色くべたつく
- 改善ポイント
- 急性胃腸炎、食中毒(細菌やウイルス感染)などが原因で胃腸に炎症が起こり、下痢をしてしまうタイプ。身体の熱を冷まして炎症を鎮め、弱った胃腸の働きを整えることが大切です。
- 摂り入れたい食材
熱を冷まし胃腸の炎症を和らげる:クチナシ、豆腐、五行草、りんご など
3 急性下痢③暴飲暴食「食の不摂生」タイプ

- 気になる症状
暴飲暴食後に起こる下痢、胃痛、腹痛、軟便、吐き気、げっぷ、膨満感、舌苔がべたつく
- 改善ポイント
- 脂っこい料理やアルコールの取り過ぎ、暴飲暴食などで胃腸に過度な負担がかかると、急性の下痢を招く要因に。まず消化を促して、胃腸の負担を取り除きましょう。
- 摂り入れたい食材
消化を促し胃腸を整える:サンザシ、麦芽、ちんぴ(みかんの皮)、大根、ヨーグルト、お焦げ など
4 急性下痢④梅雨から夏に注意「寒湿(かんしつ)」タイプ

- 気になる症状
湿気が多く身体が冷える時に起こる下痢や腹痛、お腹や手足の冷え、むくみ、顔色が白いまたは黄色い、舌苔が白い
- 改善ポイント
- 「冷え」と「湿」(余分な水分や汚れ)は胃腸の大敵。そのため、湿気の多い気候、水分の取り過ぎなどで胃腸の働きが低下すると、下痢を起こしやすくなります。梅雨から夏の時期は特に注意して、気になる症状あれば積極的にケアを。
- 摂り入れたい食材
身体を温めて湿を取り除く:シナモン、フェンネル、カルダモン、山椒の実、しょうが、梅干し など
5 慢性下痢①疲れやすい「胃腸虚弱」タイプ

- 気になる症状
下痢(軟便、消化不良)、食欲不振、お腹の張り、疲労感、無力感、痩せ、顔色が黄色い、舌の色が淡い、舌苔が薄い
- 改善ポイント
- 食生活の乱れ、病気の消耗、加齢などが原因で胃腸が弱っていると、慢性的に下痢を起こしやすくなります。このタイプは身体のエネルギーも不足しがちなので、「気」(エネルギー)をしっかり養い、胃腸を健やかに保つよう心がけましょう。
- 摂り入れたい食材
気を養い胃腸を元気に:米、いんげん豆、大豆製品、りんご、山芋、キャベツ、じゃがいも など
6 慢性下痢②肝の不調を招く「ストレス」タイプ

- 気になる症状
ストレスや緊張・不安感などで下痢が起こる、胸苦しい、胸・脇の張りや痛み、げっぷ、食欲不振、舌の色が淡い、舌苔の乾燥
- 改善ポイント
- 「肝(かん)」(肝臓)と「胃腸」は関係の深い臓器。そのため、過剰なストレスで「肝」の機能が低下すると、胃腸の働きも落ちて下痢をしやすくなります。ストレスはこまめに発散し、気持ちを穏やかに保つ心がけを。
- 摂り入れたい食材
ストレスを発散して肝の働きを整える:グリーンピース、そば、香草類、梅干し、菊花、ジャスミン など
point!暮らしのポイント
・味(辛・苦・甘・酸・鹹(かん・塩からい味))、性質(寒・熱・温・涼)、内容(穀物、果実、肉、野菜)を考え、バランスの良い食事を。
・おしゃべりや趣味を楽しんで、こまめなストレス発散を。
胃腸に効くツボ「足三里」

関連記事
この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生
1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。
1979年、来日。
1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。
症状一覧
- よくあるお悩み症状
-
- 日常の疾患
- 春の症状
- 秋の症状
- 身体の不調から症状を探す
-
- こころ
- 全身
- 子ども
- その他
- 背中・腰
-
- 手・足
CHECK!
まずは、自分の体質タイプを
チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?
対策は人それぞれ異なります。
まずは中医学の視点から
あなたの体質タイプを知りましょう。
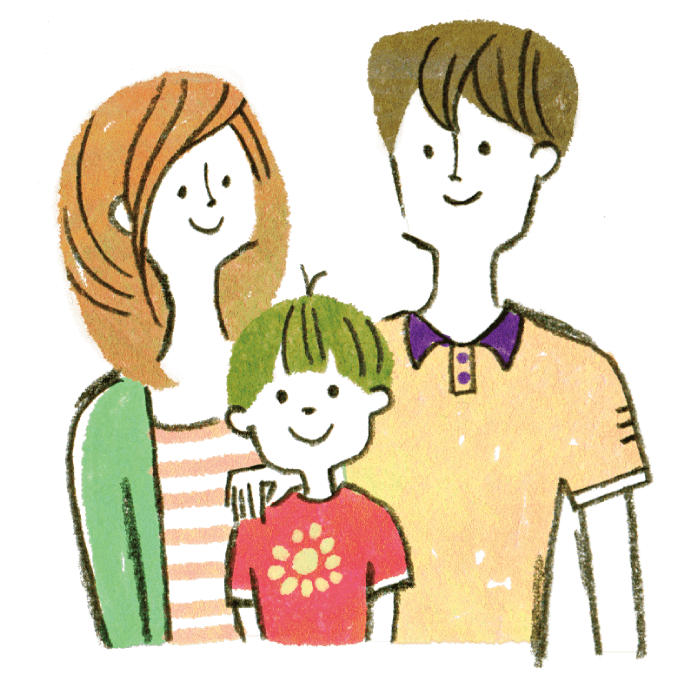
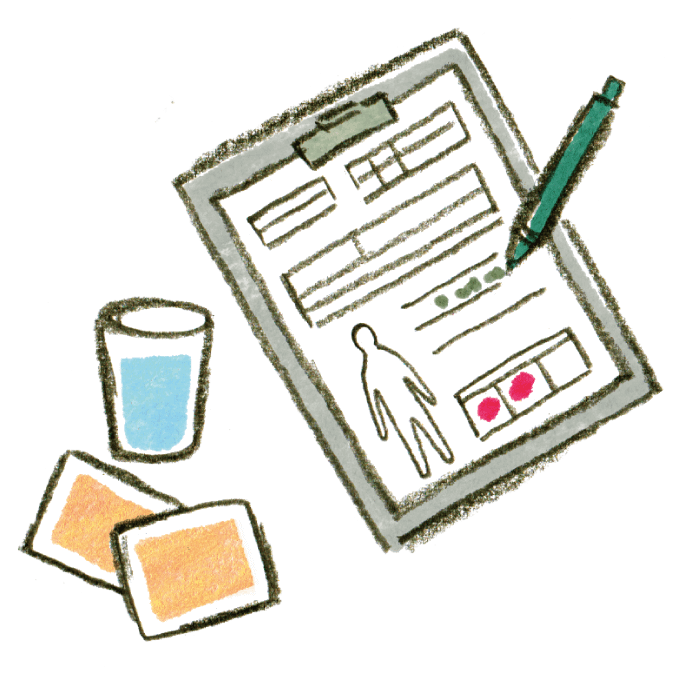
TYPEA
「元気不足」タイプ
気虚(ききょ)
エネルギーとなる気が不足しています。
疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?
TYPEB
「イライラ」タイプ
気滞(きたい)
気の巡りが滞っています。
イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?
TYPEC
「血液の不足」タイプ
血虚(けっきょ)
カラダの栄養となる血が不足。
冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?
TYPED
「血液ドロドロ」タイプ
瘀血(おけつ)
全身の血の巡りが滞った状態です。
目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?
TYPEE
「潤い不足」タイプ
陰虚(いんきょ)
カラダの潤いが不足しています。
のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?
TYPEF
「ため込み」タイプ
痰湿(たんしつ)
水分代謝が落ちた状態です。
太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?
ABOUT
中医学とは

こころとカラダのこと、
ちゃんと知りたい
中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。
![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)



