漢方の知恵袋
かぜかぜをひいたときに早く治す方法・かぜの予防方法
監修:菅沼 栄先生(中医学講師)
油断大敵!「風邪(ふうじゃ)」は万病のもと

check!かぜかな?と感じたら、早めの対策で撃退!
かぜの症状は、悪寒や頭痛などが特徴の寒(かん)、熱やのどの痛みなどが特徴の熱(ねつ)、吐き気や下痢などが特徴の湿(しつ)、咳などが特徴の燥(そう)の4つのタイプがあります。
それぞれの症状には特徴があるので、そのタイプに合った対処法を知ることが大切。今かぜをひいている方は、自分自身がどんな症状なのかを念頭におきながら読んでみてください。
それでは、中医学の知恵を活かした食と暮らしの養生法(ようじょうほう。健康を維持するための方法)を症状別にご紹介します。
1 ぞくぞくする初期症状「寒」のかぜ

- 気になる症状
「寒」のかぜは、ぞくぞくっとする悪寒や頭痛、関節の痛み、肩コリ、透明な鼻水などが特徴です。かぜの初期にあたる症状で、熱の自覚症状は軽く、汗もあまりかきません。
- 改善ポイント
- この時期のかぜは、身体を温めて邪気「寒(かん)」を取り除くことが大切。白菜、大根、ネギを煮込んだスープ「三白湯(さんはくとう)」は、身体をポカポカに温めてくれます。このスープに、発汗を促すショウガや、三つ葉などの香草を加えるのもおすすめです。辛みのあるニンニクにも発汗作用があるので、すり下ろしてお湯を注ぎ“ニンニク湯”にして飲んでみてください。
- 摂り入れたい食材
三白湯(白菜、大根、ネギ)、ショウガ、香草(三つ葉など)、ニンニク
2 のどの痛みと高い熱「熱」のかぜ

- 気になる症状
「熱」のかぜは、発病したときから熱が高く、のどの腫れや痛み、黄色く粘りのある鼻水や痰、のどの渇きといった症状が現れます。
- 改善ポイント
- 塩水やお茶でこまめにうがいをし、外出から戻ったら手洗いも忘れずに。部屋の空気をよく換気することも大切です。解毒作用のある酢と水を1:2の割合で鍋で煮立てて蒸発させ、部屋の空気を消毒するという習慣も中国では一般的なので、ぜひ試してみてください。ゴボウをみそ汁の具に加えたり、菊花茶、ミントティー、板藍茶(ばんらんちゃ)などのお茶を飲むようにすると良いでしょう。
- 摂り入れたい食材
ゴボウのみそ汁、菊茶、ミントティー、板藍茶
3 胃腸に来る「湿」のカゼ

- 気になる症状
「湿」のかぜは、胃のムカつきや吐き気、痛み、下痢、食欲不振など、消化器系の症状が現れる胃腸型のかぜ。
- 改善ポイント
- 胃に不安のあるときは、生ものや油っこい料理はなるべく避けるようにしましょう。米は、消化しやすいようおかゆにして食べるのがおすすめです。おなかを温めて胃の痛みを和らげる八角や山椒の実、解毒作用のあるニンニクやシソ、ショウガなどをうまく料理に活用してください。
- 摂り入れたい食材
シソ、ショウガ、ニンニク、八角、山椒の実
4 咳がつらい「燥」のかぜ

- 気になる症状
「燥」のかぜは咳が強く、痰がからんで胸に重苦しさを感じることも。呼吸器系の弱い人に多く見られる、治りかけの時期の症状です。
- 改善ポイント
- マスクや加湿器などで湿気を補い、肺を潤すように心がけましょう。梨を皮ごと蒸したものや、銀杏入りの茶碗蒸し、百合根のみそ汁、杏仁豆腐、大根の煮物など、肺を潤す食べ物を食事のメニューに加えてみてください。
- 摂り入れたい食材
梨(皮ごと蒸して)、銀杏入りの茶碗蒸し、百合根のみそ汁、杏仁豆腐
point!体力を養ってかぜを寄せつけない身体に
また、冬のかぜを予防するには、寒さから身体を守ることも大切です。外出する際は手袋やマフラーなどを用意し、なるべく暖かな服装を心がけてください。寝る前にお風呂に入り、よく体を温めるのも良いですね。お風呂は、ぬるめのお湯に長くつかることがポイントです。あつあつの鍋料理や、ネギ、ニンニク、ショウガなどは、身体を温めて発汗を促す効果があるので、上手にとり入れてみてください。月刊誌『チャイナビュー』(イスクラ産業発行)より掲載
関連記事
この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生
1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。
1979年、来日。
1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。
症状一覧
- よくあるお悩み症状
-
- 日常の疾患
- 春の症状
- 秋の症状
- 身体の不調から症状を探す
-
- こころ
- 全身
- 子ども
- その他
- 背中・腰
-
- 手・足
CHECK!
まずは、自分の体質タイプを
チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?
対策は人それぞれ異なります。
まずは中医学の視点から
あなたの体質タイプを知りましょう。
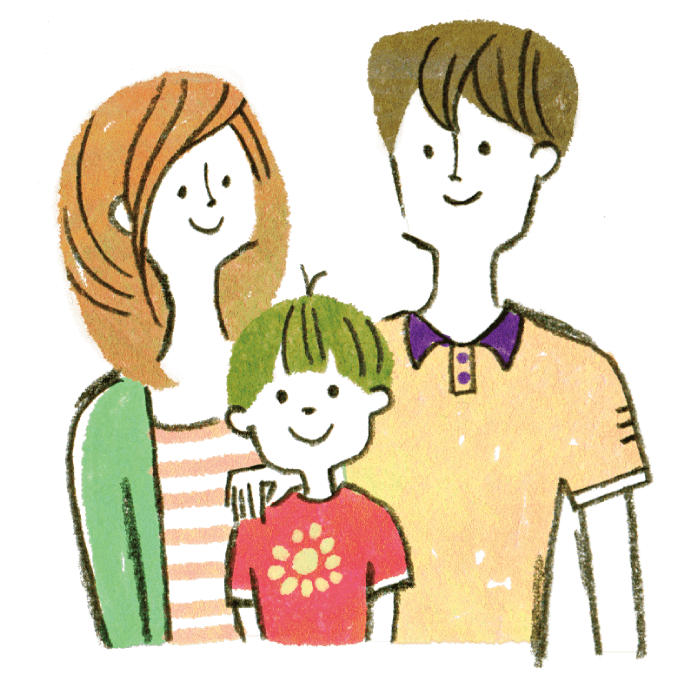
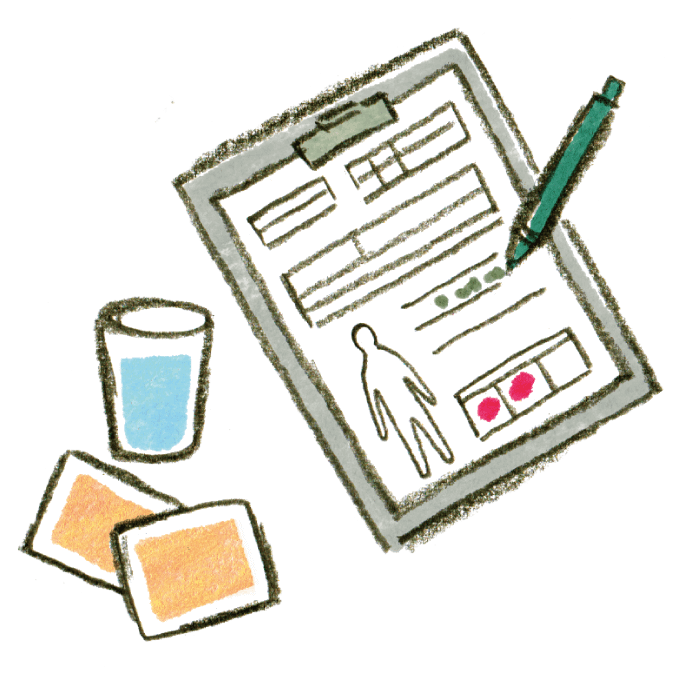
TYPEA
「元気不足」タイプ
気虚(ききょ)
エネルギーとなる気が不足しています。
疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?
TYPEB
「イライラ」タイプ
気滞(きたい)
気の巡りが滞っています。
イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?
TYPEC
「血液の不足」タイプ
血虚(けっきょ)
カラダの栄養となる血が不足。
冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?
TYPED
「血液ドロドロ」タイプ
瘀血(おけつ)
全身の血の巡りが滞った状態です。
目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?
TYPEE
「潤い不足」タイプ
陰虚(いんきょ)
カラダの潤いが不足しています。
のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?
TYPEF
「ため込み」タイプ
痰湿(たんしつ)
水分代謝が落ちた状態です。
太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?
ABOUT
中医学とは

こころとカラダのこと、
ちゃんと知りたい
中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。
![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)


