漢方の知恵袋
認知症原因を知ってイキイキ長生き!脳の老化を予防しましょう
監修:菅沼 栄先生(中医学講師)
身の回りの家族・親戚などで認知症にならないか不安に思ったことはありませんか?もしくは将来自分が認知症になったらどうしよう、と思っている方もいるかもしれません。
できることは何もないのでしょうか?認知症にならないためにできることはあるんです。
この記事では、中国の伝統医学である中医学をもとに、脳の老化を予防する方法を分かりやすく説明します。元気な今から積極的にケアをして、いつまでもイキイキと健やかな毎日を過ごしましょう!
認知症の原因を大きく分けると4つ
check!認知症の予防法をタイプ別にチェック!
中医学の考えでは、認知症は上で挙げた4つのタイプに分けられます。それぞれ症状には特徴があり、効果的な予防法も異なります。自分があてはまるタイプを考えて、日頃の生活から認知症の予防を心がけましょう。
1 血液ドロドロ「瘀血(おけつ)」タイプ

- 気になる症状
物忘れ、頭痛、顔色が暗い、手足のしびれ、舌の色が暗い
西洋医学の「脳血管性認知症」にあたるタイプ
- 改善ポイント
- 【高血圧や動脈硬化などが気になる人は要注意】年齢を重ねると血液も粘りが出るため、血の流れが滞り瘀血を生じやすくなります。瘀血は脳への血流をさまたげ、それが健忘や痴呆といった症状を引き起こす原因となります。
このタイプの主な症状は、物忘れや頭痛、疼痛、手足のしびれ、顔色が暗いなど。高血圧、動脈硬化、狭心症、高脂血症、脳血管障害といった症状が見られる人のほか、手術歴や大きな外傷歴がある人は、このタイプの認知症に注意が必要です。血液をサラサラにして流れを良くする「活血(かっけつ)」「化瘀(かお)」、脳を健やかにする「健脳」などを中心に、予防・対応していきましょう。 - 摂り入れたい食材
黒いもの、辛味のあるものなどを意識して摂るようにしましょう:
昆布、わかめ、黒酢、山査子(さんざし)、小豆、黒きくらげ、ラッキョウ、黒豆、酒(少量)、にんにく、たまねぎ、セロリ
2 老化が進む「腎虚(じんきょ)」タイプ

- 気になる症状
健忘、腰痛、めまい、聴力の減退、脱毛、歯が弱い、夜間の頻尿
西洋医学の「アルツハイマー型認知症」にあたるタイプ
- 改善ポイント
- 【さまざまな老化現象は腎虚が原因に】「老化の進み方の差は、腎虚の進み方の差」と中医学では考えられています。腎は、「精」と呼ばれる、生命を維持するエネルギー源の貯蔵庫となっています。そのため、腎の機能が低下すると、骨や歯がもろくなる、排尿がうまくいかない、といったさまざまな老化現象が現れます。認知症もその一つ。このように、認知症に限らず老化現象を予防するためには、腎を養う「補腎(ほじん)」、精を増やす「益精(えきせい)」が大切。老化をなるべく穏やかにして元気な身体で老後を過ごせるよう、日頃から少し気を配ってみてくださいね。
- 摂り入れたい食材
味のしっかりしたもの、動物性のものなど、補腎の効果がある食べ物を:
きのこ類、クコの実、白きくらげ、にら、くるみ、すっぽん、黒ゴマ、松の実、うなぎ、霊芝茶
3 エネルギー不足の「脾気虚(ひききょ)」タイプ

- 気になる症状
食欲不振、息切れ、疲労、不眠、健忘、風邪をひきやすい
- 改善ポイント
- 【食欲や体力が落ちたなと感じたら気をつけて】「脾胃(ひい)」(消化器系)は「気血」を生む源。脾気が身体に栄養を運び、その栄養から血が生まれます。そのため、脾胃が弱くなると全身の気血が不足し、五臓六腑(内臓)はもちろん、脳の機能も低下してしまうのです。胃が弱い人、慢性疾患や老化などで体力が落ちている人は、このタイプの認知症に注意が必要です。
- 摂り入れたい食材
甘みのあるもの、補う効果のあるものを中心に食材選びを:
栗、米、麦、ライチ、ぶどう、いんげん豆、にんじん、りんご、豆腐、湯葉、大豆製品
4 ストレスが多い「肝鬱(かんうつ)」タイプ

- 気になる症状
情緒の不安定、憂鬱、イライラ、胸脇脹満、不眠、悪夢、集中力の低下
- 改善ポイント
- 【イライラやストレスは認知症の悪化に】肝は新陳代謝をコントロールする大切な臓器。この機能がうまく働いていると、全身にきれいな酸素がいきわたり脳の働きも活発になります。肝鬱タイプの認知症は、ストレスで肝の機能が減退し、気の流れが滞ることが原因で起こります。また、気の流れの滞った「気滞(きたい)」という状態が長く続くと「瘀血(おけつ)」につながることもあります。老化への不安がストレスになるケースも多く見られますが、老化はだれにでも訪れるもの。あまり神経質にならず、上手に付き合っていきましょう。
- 摂り入れたい食材
香りの良いものなどでストレスを発散し、気の流れをスムーズに:
しそ、玫瑰花茶(まいかいかちゃ)、菊花茶、びわ、はと麦、どくだみ、冬瓜、トマト、きゅうり、みかん、緑豆
point! 老後は「本物の人生」。毎日を楽しく健やかに
関連記事
この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生
1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。
1979年、来日。
1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。
症状一覧
- よくあるお悩み症状
-
- 日常の疾患
- 春の症状
- 秋の症状
- 身体の不調から症状を探す
-
- こころ
- 全身
- 子ども
- その他
- 背中・腰
-
- 手・足
CHECK!
まずは、自分の体質タイプを
チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?
対策は人それぞれ異なります。
まずは中医学の視点から
あなたの体質タイプを知りましょう。
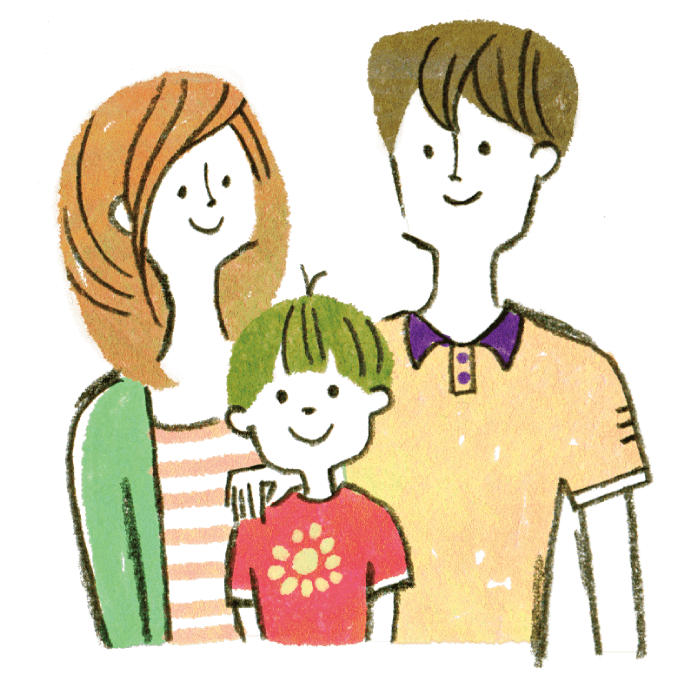
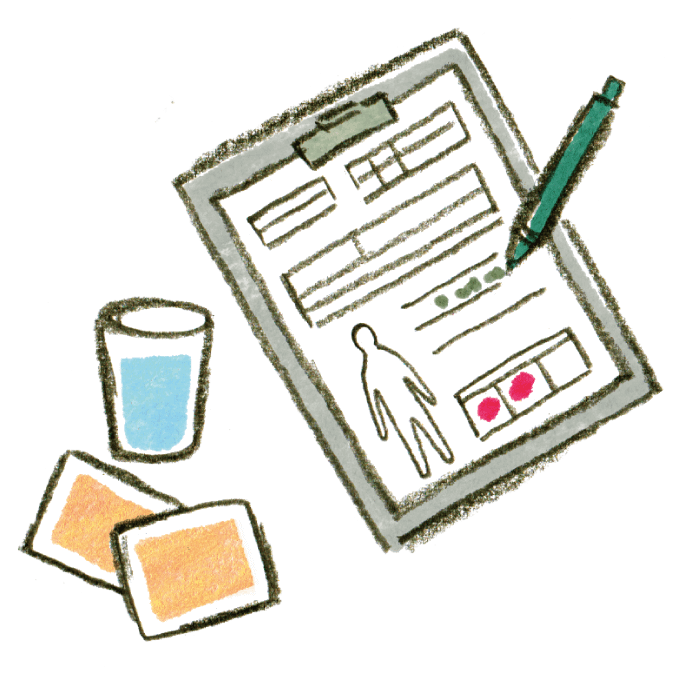
TYPEA
「元気不足」タイプ
気虚(ききょ)
エネルギーとなる気が不足しています。
疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?
TYPEB
「イライラ」タイプ
気滞(きたい)
気の巡りが滞っています。
イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?
TYPEC
「血液の不足」タイプ
血虚(けっきょ)
カラダの栄養となる血が不足。
冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?
TYPED
「血液ドロドロ」タイプ
瘀血(おけつ)
全身の血の巡りが滞った状態です。
目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?
TYPEE
「潤い不足」タイプ
陰虚(いんきょ)
カラダの潤いが不足しています。
のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?
TYPEF
「ため込み」タイプ
痰湿(たんしつ)
水分代謝が落ちた状態です。
太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?
ABOUT
中医学とは

こころとカラダのこと、
ちゃんと知りたい
中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。
![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)


