監修:楊 敏 先生(中医学講師)
こんにちは。中医学講師の楊敏です。
今回のテーマは、料理の名脇役「スパイス」(香辛料)。その豊かな香りで風味を引き立てるスパイスは、中国はもちろん世界中のキッチンで重宝されています。一方、スパイスにはさまざまな効能があることも知られ、体のバランスを整える薬膳にも欠かせない存在。上手に使えば“おいしく養生”できるので、身近なスパイスの効能を知り、ぜひ日々の食事に生かしてみてください。
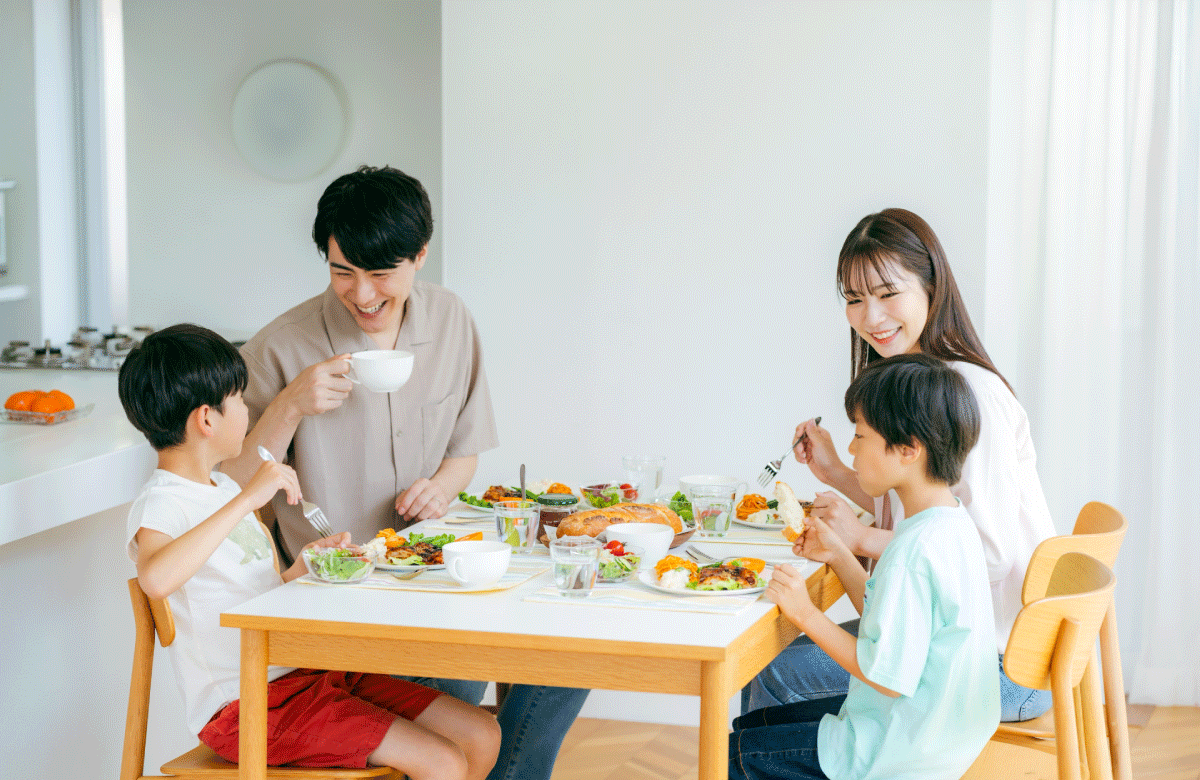
「薬食同源」。スパイスを取り入れて、健やかな毎日を
「薬食同源」という言葉があるように、中医学では「食べ物」と「薬」は同じルーツと考えます。これは、日々の食事こそ良薬であり、健康を保つ基本ということ(命は食にあり、食誤れば病に至り、食正しければ病は自ずと癒える)。実際、中国最古の薬物書『神農本草経』には365種類の薬物が記載され、その半数以上は食べ物といわれています。それほど、食と健康は深く結びついていると考えられてきたのですね。
そんな“健康に役立つ食べ物”には、スパイスもたくさん含まれます。生姜(しょうきょう/しょうが)、肉桂(にっけい/シナモン)など、ぜひその働きをセルフケアに取り入れてみてください。体質や体調に合わせて適切に使うことで、日々の食事が“プチ薬膳”になりますよ。
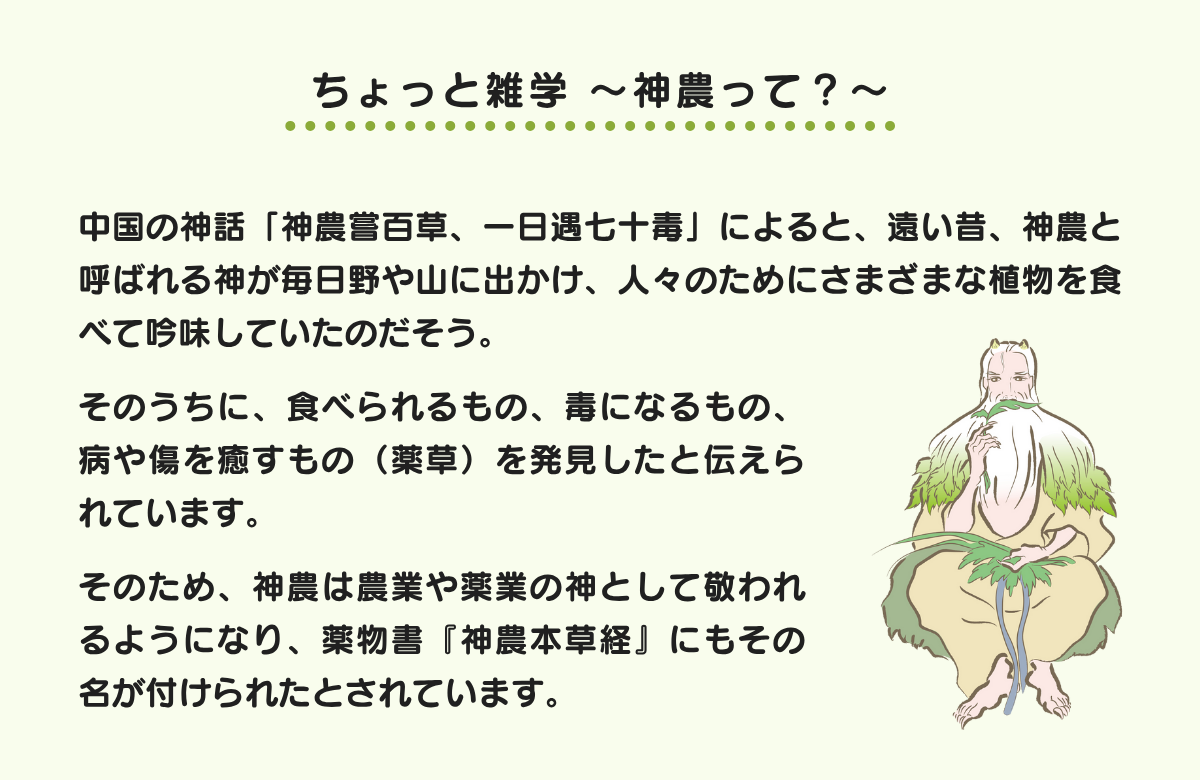
手軽に使える! おすすめスパイス8選
胃腸トラブル、かぜ、冷え、ストレスなど、身近な不調に使えるスパイスをいくつかご紹介します。手軽に取り入れられるものばかりなので、参考にしてみてください。
(1)しょうが
[特性]辛味/微温性/肺・脾・胃に帰経
〜中医学における働き〜
・体を温めて発汗させる:ぞくぞくするかぜの初期症状(寒気、頭痛、発熱など)、かぜ予防に(暑がりな人は少なめに)。
・胃腸を温める:冷えによる胃痛・腹痛、嘔吐、下痢、軟便、食欲不振などに。
・肺を温める:サラサラの鼻水、白い痰、咳などに。
・抗菌解毒:魚介類による食中毒の対策に。
〜例えば〜
・ぞくぞくするかぜを引いたら…しょうが湯、しょうが入りみそ汁
・体が冷えるときは…しょうが入り紅茶
・吐き気やつわりがひどいときは…舌にしょうがのしぼり汁を乗せる。中国では、しょうがは「嘔家(よく嘔吐する家系)の聖薬」ともいわれます。
・白い薄い痰が多く、咳が気になるときは…乾燥しょうが(乾姜)とみかんの皮(陳皮)を煎じてお茶として。
・刺し身を食べるときは…薬味として一緒に。
(2)大葉(青じそ)
[特性]辛味/温性/肺・脾に帰経
〜中医学における働き〜
・軽い発汗作用:胃腸型のかぜ症状(寒気、発熱、胃痛、嘔吐、下痢など)に。
・気を巡らせ、胃の働きを整える:胃腸の張り、胃痛、食欲不振、吐き気、ストレスによるのどの不快感などに。
・妊娠の安定:つわり、食欲不振、お腹の張りなどに。
・抗菌解毒:魚介類による食中毒の対策に。
〜例えば〜
・胃腸型のかぜを引いたら…大葉を刻んでみそ汁や鍋料理に。
・食欲不振やつわりがあるときは…しそジュース、しそふりかけ、みそのしそ巻きなどを。
・刺し身を食べるときは…薬味として一緒に。花穂紫蘇もおすすめ。
(3)パクチー(香菜、コリアンダー)
[特性]辛味/温性/肺・胃に帰経
〜中医学における働き〜
・胃を整え、消化を促す:食べ過ぎ、消化不良、胃痛、胃のつかえ、食欲不振などに。
〜例えば〜
・胃の不調を感じるときに…お粥や麺にパクチーを添えて。
・寒気や頭痛がするときに(かぜの初期)…酸辣湯やラーメンに刻んだパクチーを添えて。
(4)ミント
[特性]辛味/涼性/肺・肝に帰経
〜中医学における働き〜
・熱を冷まし、頭痛や目の充血を鎮める、消炎抗菌:発熱、頭痛、のどの痛み、結膜炎、ものもらいなどに。
・肝の働きを整え、気を巡らせる:イライラ、憂うつ、不安感、自律神経の乱れ、ストレスによる胃腸の張り・痛み、ゲップやガス、PMS、月経不順などに。
〜例えば〜
・発熱やのどの痛み、扁桃腺炎、精神不調、PMSなどが気になるときに…ミントティー、ミント飴、ミント入りのお菓子などを。

(5)どくだみ
[特性]辛味/微寒性/肺・腎・膀胱に帰経
〜中医学における働き〜
・熱を冷まして解毒する、膿を排出する、消炎抗菌、利水:肺炎や気管支炎による痰・咳・胸痛、膀胱炎や尿道炎による排尿痛、大腸炎、痔、便秘、腫れ物、湿疹、皮膚の化膿などに。
〜例えば〜
・清熱、消炎抗菌には…どくだみ茶、どくだみの葉のサラダ、どくだみの茎と鶏肉の炒めもの(にんにく、醤油、酢の味付けがおすすめ!)などを。
・腫れ物や湿疹、痔などのケアには…どくだみを煎じて、患部を洗ったり入浴剤にしたり。

(6)シナモン
[特性]辛味・甘味/熱性/腎・脾・心・肝・胃に帰経
〜中医学における働き〜
・体を温め陽気を補う、寒邪を発散し痛みを止める:体の冷えによる足腰の痛み、頻尿・夜間頻尿、不妊症、腹痛、軟便・下痢などに。
・陽気を強くして気血を補う:冷え性、めまい、経血量が少ないときなどに。
〜例えば〜
・冷えが気になるとき…シナモンティー、シナモンとなつめ入りの紅茶などを。
・寒気、頭痛がするとき(かぜの初期)…シナモン・ジンジャーティーがおすすめ。
(7)紅花(べにばな)
[特性]辛味/温性/心・肝に帰経
〜中医学における働き〜
・瘀血(血行不良)を緩和する、血行を促し痛みを和らげる:月経痛、月経不順、無月経、子宮筋腫、子宮内膜炎などの婦人科疾患、胸痛、不整脈、肝硬変など瘀血による内科疾患に。
〜例えば〜
・血行不良があるときに…紅花入りの紅茶、紅花入りの薬酒、紅花入りの料理などを。
<注意>子宮を収縮させる働きがあるので、妊娠中、月経過多の人は控えて!
(8)サフラン
[特性]甘味/寒性/心・肝に帰経
〜中医学における働き〜
・血行を促進する、痛みを緩和する:紅花と似た効能ですが、「寒性」なので暑がり体質の瘀血に。
・血の熱を冷まし、精神を安静にする:発熱、熱感が強くイライラするときなどに。
〜例えば〜
・体に熱がこもり、血行不良やイライラがあるときに…サフランティー、パエリア(サフランライス)などを。
<注意>子宮を収縮させる働きがあるので、妊娠中、月経過多の人は控えて!

参考:『中薬学』(上海科学技術出版社)
この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生
楊 敏(よう びん)
上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。
1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。
主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。
![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)





